学校・企業・自治体を巡る情報操作の最前線
セキオ、前回の話で、企業や自治体も狙われてるってあったけど、もっと詳しく教えて。
もちろんだよ。まず企業から説明しよう。たとえば、2021年に某大手衣料品メーカーが中国新疆ウイグル自治区に関する人権問題に言及したところ、中国国内で大規模な不買運動が発生した。SNS上でハッシュタグが爆発的に拡散され、店舗の閉鎖に追い込まれる事態にまで発展した。
一企業の声明で、そんなに影響が出るの!?
出るんだ。背景には、中国国内の愛国主義的ネット世論の存在と、それを後押しする政府の戦略的な情報誘導がある。一般ユーザーに見せかけた国家系アカウントや、政府系メディアが火をつけることで、企業の信用を一気に毀損できる。
企業はどう対策してるの?
最近では、多くの企業がSNS監視ツールを導入し、炎上リスクを早期に察知しようとしている。また、ステートメントの発表タイミングや表現方法にも細心の注意を払うようになった。特に地政学的に敏感なテーマでは、事前にリスク分析を行うようになってきているよ。
学校も狙われるんだよね?
そう。たとえば、ある高校の歴史授業で近現代史を扱ったところ、特定の政治団体が「偏向教育」として糾弾。SNS上で教員の実名や顔写真が晒され、PTAや教育委員会が抗議対応に追われた事例がある。
そんなの先生が気の毒すぎるよ。
本当にそうだね。しかもこの手の騒動では、一部の発言や教材内容を切り取って拡散されるから、文脈が完全に無視されてしまう。報道もセンセーショナルに取り上げるから、冷静な対話が難しくなる。
教育現場への影響って大きいの?
大きいよ。学校は立場上、政治的中立が求められるけど、攻撃されると自主規制が強まり、萎縮が起きる。結果的に、生徒たちが多様な視点に触れる機会を失うことにもつながるんだ。
自治体も似たような問題を抱えてる?
自治体は国際関係が絡む場面で特に狙われやすい。たとえば、ある市が台湾と文化交流を進めたところ、中国側から強い反発があり、SNSやメールで大量の抗議が届いた。市のホームページがサイバー攻撃で一時的にダウンした例もある。
そんなことまで?サイバー攻撃って国家レベルじゃん。
そう。でも最近では、国家機関が直接ではなく、親中団体や関連企業を通じて圧力をかけるケースも増えている。表向きは民間の声として見えるから、より自然に影響を与えられるんだ。
職員の個人情報が晒されることもあるって言ってたよね。
うん。中には特定の判断を下した自治体職員の氏名や顔写真がSNSで拡散され、「辞職しろ」といった脅迫的コメントが寄せられたケースもある。精神的なダメージは大きく、内部での検閲や萎縮につながる。
もう完全に民間ドメインまで戦場なんだね…。
まさにその通り。民間は無関係だと思っていた時代は終わったんだ。情報戦の最前線は、社会のあらゆる場所に拡大してるんだよ。
ぼくももっと慎重に情報を見なきゃ。
それが大切だよ。誰かの意見に流される前に、「これは誰が言ってる?」「何を目的としてる?」って考える習慣が、何よりの防御策になるんだ。
でも、どうやってその「誰が言ってるか」って見分ければいいの?
投稿元のアカウントをチェックするのが第一歩だね。作られたばかりのアカウント、投稿が偏っているアカウント、プロフィールが曖昧なものには注意したほうがいい。
なるほど。たとえば、変な外国語のアカウントとかも怪しいのかな?
そうだね。日本語が不自然だったり、投稿時間が現地時間に合っていない場合は、海外の情報工作アカウントの可能性もあるよ。
なるほどね。。気を付けて情報を精査していかないとだね。
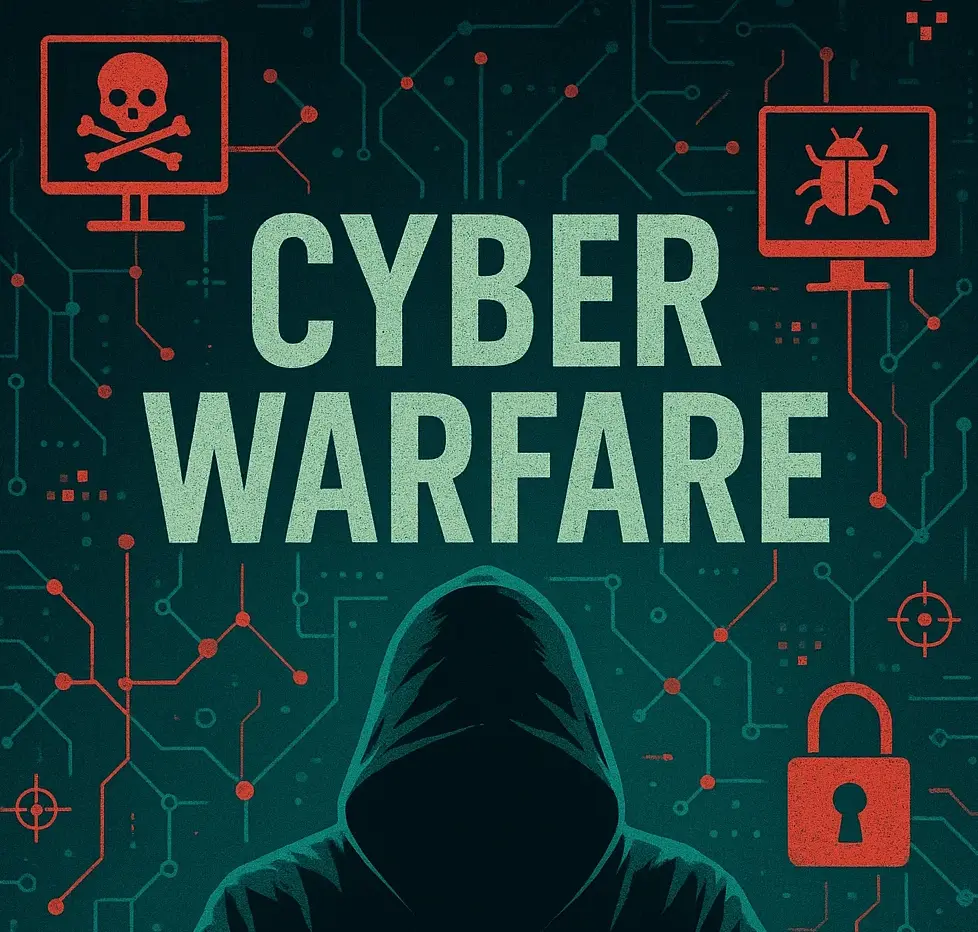


コメント